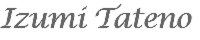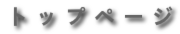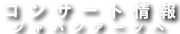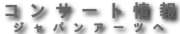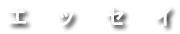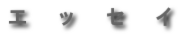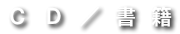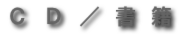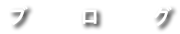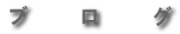小自叙伝
1936年(昭和11年)11月10日東京目黒区緑ヶ丘生まれ。父弘(チェリスト)は栃木県間々田、母光(みつ、ピアニスト)は仙台生まれだが、育ちは室蘭。二人とも武蔵野音楽学校創成期に学ぶ。母方の小野家は明治維新まで七代にわたって、仙台伊達藩の能楽を司っていた。祖母かつは、ヴァイオリンも弾いたが、母には、琴、三味線を習わせたがり、子供の頃の母は、それが嫌で押し入れに隠れたりしたという。室蘭の家の近くの長屋に、とても美味しいパン屋があり、職人気質の主人が釜で焼くそのパンは、絶品だったそうだが、どういうわけか、嫁さんがひっきりなしに替わったとか。母の遊び友達だったそこの娘が、「今度のお母ちゃんは、義太夫が上手で、レコードも吹き込んだ」と自慢していたそうだ。
祖父誠は、眼科医。手術では日本三名医の一人といわれたそうだが、酔うと電信柱に登る癖があり、室蘭時代は交番の駐在さんから、小野先生がまた電柱に登って下りてこないと、よく注進があったらしい。母を頭に10人の子を生ませて、50代も半ばで亡くなった。かつ婆さんは、「誠さんはずるい。私を愛して愛して、さっさと黄泉の国に行ってしまった。」とぼやいていた。私の両親は、若い頃は室内楽をしていて、父は、永井進氏などともピアノ・トリオをしたが、後には双葉音楽研究所という私設の音楽教室を開き、ピアノやチェロなどを教えていた。
私が生れた夜は、シラーの「群盗」の劇音楽を弾きに出かけ、帰ってみたら、きゅうりのように青くて長い顔の赤んぼがいたとか。その緑ヶ丘の家には、若い音楽仲間や演劇青年も出入りし、まだ無名の頃の宇野重吉さんも来て、芝居の稽古をしたそうだ。初心と好奇心に燃える若者の集まりだったのではないか。父は、音楽をすることほど素敵な人生はないと、一生思っていた人だった。
初めての子供にと、父の姉が紙に書いてきた名前は「多吉」と「為吉」。普段は口数の少ない母の反対で「泉」に落着いたそうだが、舘野多吉や為吉だったらピアニストになっていただろうか。もしなっていたら、どんな芸風だったろうかと想像するのも結構楽しい。
初旅は一歳になる前の両親の北海道演奏旅行。函館の埠頭で撮った写真がある。当時は、汽車と船で長い旅だっただろう。岩手、青森の山間部を走ると、列車食堂の残飯を追って子供と鳥が集まってきたという。きゅうりは、札幌の日本放送協会のスタジオで両親が演奏中、調整室で泣いていてた。聞くも哀れ、流浪する音楽家の宿命は、この旅で既に深く刻みこまれたのだ。仙台の家で深夜、重い響きをたてて走り行く蒸気機関車の、胸をうずかせるような警笛によく聴き入った。あれは、どこに行くのだろう。遠く、北のほうに?その響きに連れられて、北欧まできてしまったと思うことがある。音には、人の魂を遠くに連れていってしまう、そんな魔力が潜んでいる。
五歳の五月五日から正式にピアノの勉強を始めた。だからタンゴが好きだ、なんて言わない。父が、竹針の蓄音器でタンゴはよく聴いていたし、フラメンコを見て感激し、帰宅してから子供たちを前に、床の間で踊ってくれたこともある。楽しい人だった。幼時に圧倒的な感銘を受けた音楽はチゴイネルワイゼン。本の虫で、物語の世界に入ってしまうと、傍で大声で呼ばれても聞こえなかったらしい。いつも首をかしげて、この子は一体何を考えているのだろうと、父は思ったそうだ。音楽に合わせて即興で物語を作りながら、父はピアノを教えてくれた。幻想の中に没入して、夢の世界で泣いたり笑ったりする子だったから、語り手も張合いがあったらしい。近所に紙芝居の小父さんが太鼓を叩いて触れにまわると、一番最初に駆けつけたが、「飴を買わない子はあっちあっち」と言われて、いつも遠くから見ていた。家計が苦しい時でも、本や楽譜は買ってもらえたが、小遣いは貰ったことがない。
小学校の入学式から帰った日「お母さん、僕の学校では君が代がデス(レのフラット)から始まるんだよ」と首をかしげたとか。伴奏のオルガンのピッチが下がっていたからだが、当時の軍部が聞いたら「国家の尊厳を半音も下げおって不謹慎な」と怒ったかどうか。学校のピアノは二階の音楽室にあったが、戦後盗まれたことがある。雪が降った夜で、警官がリヤカの轍の跡をつけると、防空壕に隠されていた。間の抜けた話だが、盗んだのは近所の男二人。たった二人で二階から運び出したのだから凄い。
終戦の年の4月、東京大空襲の際に我が家は焼夷弾の直撃をくらって全焼。我々が退避していた粗末な防空壕は、ほんの数メートルしか離れていなかった。鉄骨だけ残ったピアノを見てもそれほど悲しくなかったが、宮沢賢治の「風の又三郎」や「西遊記」などの愛読書の焼けてしまったのが悲しかった。終戦までの数ヶ月、栃木県間中の思川のほとりに疎開。ピアノなど勿論ない。東京でさえ、ピアノを弾いていると家の中に泥を投げ込まれた時代だ。朝礼でお稲荷様にお参りし、小学校は上級と下級の2クラスだけ、裸足で田畑を駆け回り、蚕と同じ部屋に寝起きしたその数ヶ月は、私の人生で量りしれぬ大きな(肯定的な)重みをもっている。
終戦の翌年、まだ焼野原ばかりの東京で、全日本学生音楽コンクールが開催された。凄まじい戦争が終わったばかりの混乱期に、全国規模の子供のためのコンクールが催された、その辺が日本という国の凄いところだ。小学4年の私は、ドビュッシーの《子供の領分》を弾いて2位に入賞。日比谷公会堂での受賞者演奏会では、自分の出番直前まで遊びに夢中で、いざステージで演奏中、尿意のひどいのに気がついた。《ゴリウォーグのケークウォーク》を弾き終わるなり、脱兎のように前を押さえて楽屋に飛び込んだのが、当時日本最高の檜舞台であった日比谷公会堂でのデビュー始末記。翌年には初めてオーケストラと共演。曲はハイドンの協奏曲ニ長調。次の年にはパデレフスキーの《主題と変奏》を弾いて1位に。「詩的であり、北欧の憂愁をたたえた各変奏曲を感情豊かに弾きわけた」とは村田武男氏の評。小学校では一番のちびで、前にならえをしたことがなく、ペダルに足が届かなくて、スリッパの下に厚いフェルトを縫いつけたものを使用。昨今の底厚靴のギャルみたいだ。ニュース映画にも撮られた。
小五の年から豊増昇氏に師事。戦後の何もない時代で、先生のお宅にも、あるのは楽譜とピアノだけだった。自分の子供のように可愛がっていただいたが、先生お得意のバッハやモーツァルトは教えていただいた記憶がない。どうしてだろう。わが家には世界大音楽全集などの楽譜があり、バルトークやミヨー、シマノフスキーやストラヴィンスキーのピアノ曲の刺激的な響きに多いに魅かれた。
緑ヶ丘の住宅街から踏切を渡ると、自由ヶ丘の駅前周辺は闇市。そこをうろつくのは禁じられていたが、面白くて毎日出かけた。食料の買い出しで満員の列車のデッキにぶらさがって、田舎まで父と芋や野菜を買いに出かけたり、学校では草野球と相撲取りに熱中した。物の不足していた時代だが、あの焼跡闇市時代は、なぜかとても明るく伸び伸びとしていて、私はとてもよい少年時代を過ごしたと思う。戦時中の精神的な飢えを満たそうと、どんな些細な文化事業にも人が集まった。響きの悪いホールで、楽器も充分でなかったけれど、胸を熱くして音楽に聴き入ったあの頃の雰囲気は忘れられない。楽器と人さえ揃えば、音楽はどこでだって出来るものと、幼い心に深く刻まれたそれが、現在も私の演奏活動の原点になっていると思う。
戦災浮浪児も多い時代。小学5年の時に、浮浪児役で芝居に出た。空襲で生き別れになった親子が、ピアノを弾く浮浪児がいるという噂がもとで再会する話だ。現実の我家は私を筆頭に4人の子供が皆音楽を学び、しかも両親のピアノの生徒が100人ほどあったから、朝から晩まで音楽が鳴り響いていた。小さな家で防音などもなく、音のいっぱい溢れたあの家は、いまでは奇跡だったとしか思えない。
中学は慶應普通部で、そのまま慶應高校に。塾だ、将来の就職だなどということのない幸せな時代で、考古学研究会に入部して、日吉の貝塚掘りに汗を流した。歴史や地理にはとても心を魅かれ、考古学者になりたいと思ったことも。これも私の重要な背景に違いない。古本屋で偶然見つけたセルマ・ラーゲルリョフの小説に魅かれ、以来北欧文学の世界にのめりこむ。高校初年の頃、豊増先生に「ドイツものでなく、近代の音楽も勉強したい」とアピールして与えられたのが、グラナドスの《ゴイェスカス》。これには痺れた。妖艶な響きとリズム、華麗なピアノ書法は、ずきずきと血をうずかせた。高校二年の時に、中古の小さなグランドピアノを買ってもらった。それまではずっとアプライトだった。嬉しくて、学校の昼休みに、往復一時間の道をピアノを触りに帰ったので、昼は食べなかった。その頃は楽譜を漁りにいくのも楽しみのひとつ。ドイツ系の固い楽譜ばかりの時代に、毒々しい銀蝿のような表紙のショスタコヴィッチの第一協奏曲の譜を手にしたときの感激は忘れられない。家にはレコードはなく、いつも誰かが楽器を弾いているので、ラジオも聴けなかったから、聴きたい曲の放送があると知人の家で聴かせてもらった。少年時代に聴いたバルトークの2番、プロコフィエフの3番などのピアノ協奏曲は、深く心に刻まれている。レフ・オボーリンの演奏で聴いたハチャトリアンの協奏曲は、私の最も得意とするレパートリーとなった。慶應高校が催してくれたリサイタルで弾いたムソルグスキーの《展覧会の絵》も、わが生涯のレパートリー。
高2の時より、レオニード・コハンスキー氏に師事。氏の伝えてくれる音楽的メッセージの大きさに、蘇る思いをした。ピアニスト舘野泉の大恩人である。ショパン、シューマン、リスト、ブラームスなどのほかに、スクリアビンやラフマニノフ、プロコフィエフなど、当時私が心を魅かれていた作品を勉強した。だが、芸大入試でつまずき、一年浪人。実に幸いだったと思う。文学と音楽と、自分の好きなものに存分にのめり込めたからだ。芸大では安川加壽子さんのクラスに。コハンスキー、安川の両師ともに課題はくれず、私が自分で選んだ曲をもっていった。セヴラックの組曲《ラングドック地方にて》をもっていって、「あなた、どうしてセヴラックを知っているの」と安川先生に驚かれたこともある。芸大4年の時には、妹晶子(ヴァイオリン)、弟英司(チェロ)も芸大で、税金泥棒と言われたりした。在学中に同大オケとリスト、グリーグ、ガーシュインのラプソディー・イン・ブルー、プーランクの《2台のピアノのための協奏曲》を演奏。ガーシュインでは、浜中浩一の見事な冒頭のソロに仰天。指揮は若杉弘。バルトークの《2台のピアノと打楽器のためのソナタ》やショーソンの《ヴァイオリン、ピアノと弦楽四重奏のための協奏曲》、ショスタコヴィッチのピアノ・トリオなども弾いたし、フィンランドの作曲家パルムグレンの第二協奏曲《河》の楽譜も手に入れて、芸術祭で演奏した。指揮を、その頃まだ芸大にいた山本直純に頼みにいったら、はんぺんのように白く痩せ、目つきだけは鋭く、学生なのにもう同棲(後の奥さんと)していて、こういうのが天才なんだと感じ入った。後に髭を生やし、でっぷり肥って眼鏡をかけ「でっかいことはいいことだ」などと指揮をしているから、また仰天。若杉は最初声楽科にいて、その伴奏をよく付き合ったが、シューベルトの《ガニメード》など、喉ちんこを突き出して歌っていたのを覚えている。指揮にかわってよかった。在学中にはシャンソンの芦野宏の伴奏もしたし、ジャズやタンゴ、民謡など音楽のあらゆるジャンルに興味があり、実際に演奏もしたのが、今の自分の大きな糧になっていると思う。
4年の時に、東京室内交響楽団とショスタコヴィッチの第一協奏曲を、日比谷公会堂で演奏。この時初めて燕尾服を仕立てたが、出来が悪くて、なんとなくおかま風に首のあたりが立ってしまうので、好きではなかった。69年から燕尾服をやめて、ハイネックのパンタロン・スーツなどを使い始めたのも、この辺に遠因がありそうだが、燕尾服でなければという考え方もおかしいと思っていた。音楽を邪魔しない美しさなら、何を着ても良いのではないか。
60年に芸大を卒業し、9月28日に第一生命ホールでデビューリサイタル。プロとして自活を始めたこの年から、自分の演奏歴を数えている。ヴァイオリンのジャンヌ・イスナールさんや植野(現服部)豊子さんなどと、沢山室内楽の仕事をさせていただけたし、全国の労音を中心にリサイタルも多かった。64年ヘルシンキに居を移すまでに、日フィル、東フィル、東京交響楽団、N響、インペリアル・フィル、ABC響などと数十回共演しているが、その頃一番沢山弾いたのはベートーヴェンの《皇帝》とガーシュインのラプソディー・イン・ブルー。石丸寛と共演の多かったガーシュインは日本一と言われたが、《皇帝》はもう弾きたくない。私には全然合わない曲だから。
デビューリサイタルは大成功。でも安川さんからは「第1回は誰でもうまくいくのよ。2回目で成功したらそれがプロとしての踏み出し」と言われた。第2回は翌年、三善晃、平尾貴四男のソナタなどの邦人作品のみで、「そんな曲目じゃ、誰も聞きにきてくれないよ」と皆から言われたが、これも成功。その年の音楽新聞選考の新人ベストテンに選ばれた。選考評「常に前進と変貌を続けるピアニスト。今日の彼は昨日の彼ではなく、明日の彼は既に昨日の彼ではない」は、40年後の間宮芳生氏の言葉「舘野さんは年々予測不可能な領域に足を踏み入れてゆく」に繋がっているだろう。ちなみに邦人作品は40年間ずっと弾き続けてきた。矢代秋雄、間宮芳生の第2、第3、野田輝行などのピアノ協奏曲の海外初演など、邦人作品のレコーディングも日本のピアニストでは一番多いと思う。
62年に初めてのヨーロッパ旅行。半年間北欧4ヶ国、旧ソ連、ドイツ、フランスなどを歩き、パリとヘルシンキに2ヶ月ずつ住む。フィンランドの数カ所とパリではコンサートもした。64年3月、東京でメシアンの《幼子イエズスにそそぐ20のまなざし》の全曲日本初演。全身に媚薬が巡るような響きと、激烈なリズムに酔いしれた。八村義男その他の作曲家たちが、暗譜で弾くかどうかの賭けをしたらしいが、残念ながら駄目だった。記憶力はとてもよく、暗譜に苦労したことはなかったが、メシアンは暗譜出来なかった最初の曲だ。64年、しばらくのつもりでヘルシンキに移住。キャリアも順調にスタートしていたのに何故北の最果てにと、皆から反対された。キャリアを積むならロンドンやニューヨーク、勉強するならウィーンやパリなどと言われたが、どちらにも興味はなかった。権威や組織、伝統だのお墨つき嫌いはいまも変わらない。文学を通して憧れていた北欧に住むこと、西でも東でもなく、重い伝統や権威などなくて、日本にも中欧にも適当な距離をおいて孤独でいられるフィンランドがよいと思った。スエーデンやデンマークは西欧に近すぎるとも思った。60年代のフィンランドは本当に地の果てみたいに寂しく澄んでいて素敵だった。時々、フィンランドに留学と紹介されることがあるが、私はどこにも留学したことはないので、留学と言ったことも書いたこともない。ましてや、北欧の音楽を勉強に行ったわけでもなかった。64年にヘルシンキ・デビューリサイタル。三善晃のソナタとシューマンの《謝肉祭》が前半で、後半はラフマニノフとプロコフィエフ。7紙に絶賛の評が出た。翌年春から、ヘルシンキ音楽院で教えるようになる。リサイタルや各地のオーケストラとの共演が続き、好運であった。クルト・マズアの指揮でプロコフィエフの2番を弾いたこともある。68年春、メシアン・コンクールに参加して第2位。ブルーノ・マデルナ指揮のストラスブール打楽器グループとメシアンの《7つの俳諧》を弾いた。その秋の東京のリサイタルでは、ベートーヴェンの《テンペスト》とショパンのソナタ第3番、バルトークの組曲《戸外にて》、スクリアビンのソナタ第6番、武満徹の《遮られない休息》を弾く。「ユニークな感性を持った人だ。表現される音楽は繊細で微妙である。やわらかく、そっといつくしむがごとく音を出し、作品の心情を歌いあげる。だからといって、決してめめしいのではない。音楽をこれほど余韻たっぷりと歌いあげられる人は、いまの日本にはいないのではないか。しかも余韻たっぷりと歌いあげながら、変にロマン的な感情はこの人の演奏にはない。さわやかなのである」岩井宏之氏の評。当時、現代音楽最先端のコンクールに上位入賞しての帰国リサイタルがこんな風で、やはり変わりものだったかもしれない。69年春のストックホルムとオスロのリサイタルでは、スクリアビンの第3ソナタ、バルトークの《戸外にて》、矢代秋雄のソナタにラヴェルの《夜のガスパール》を弾いて、ギーゼキングの再来と評された。このプログラムは凄かったと、いまでも思う。
70年から東芝EMIの専属になり、レコーディングを開始。以後の30年間で約100点のLP、CDをリリースした。デビュー盤は東芝の要求でショパンだったが、第2作はヤナ-チェックの《草陰の小路にて》と、私に捧げられたラウタヴァーラのソナタ第1番《キリストと漁夫》だった。大木正興氏はライナーノートに、次のように書いている。「彼の演奏はフィンランドに行く前からひとつのはっきりした個性をもっていた。作品に対面したときに、彼の心にはふつふつと新鮮な感動が沸きあがるように思われた。それは何の既成観念にも毒されない、全く舘野自身がみずから素手で発見した音楽的感動ともよぶべきもので、同じ曲を何度演奏してもその新鮮さが失われないほど、彼の音楽感受力はいつも新しかった。彼は根源的には叙情家だと思うが、それだけではなく、彼の芸術を形成するもうひとつの極めて重要な性格がある。ひとことで言えば、それは硬骨な個性なのである。一種鉄筋ともいうべき強くすくっと立った心の中の支柱こそ、彼の音楽を形成する最も重要なもので、それに天性の叙情がまつわり美しい花をつけているのである。」
72年にマックス・ファクターの男性化粧品のTVコマーシャルに登場。ファンクラブも結成された。どちらも、クラシックの演奏家としては当時異例のことであった。80年代はヘルシンキ・フィルや東フィルの海外公演のソリスト、そして欧米などのほかにインド、東南アジアの諸国、中国、中近東などにしばしば演奏旅行をするようになった。音楽の商業主義にまだ毒さていないこの地域で演奏することは好きで、これからも蒙古やチベット、ブータンなどで演奏出来たらと夢見ている。
90年代に入ると、幾つもの音楽祭の監督をするようになり、新世紀に入る頃から岸田今日子さんとの「音楽と物語」のシリーズを始めたり、アイスランドの美女二人とタンゴを弾いてまわっている。今年は45年抱き続けた夢がかなって、セヴラックのピアノ曲のCD2枚組をリリース、8月にはノルドグレンが捧げてくれたピアノ協奏曲を初演、10月には岸田さんと間宮芳生さんの新曲《よだかの星-朗読付きピアノ・ソナタ第4番》も初演する。
60年ピアノを弾き続けてきた。失敗も沢山あり、よい批評、悪い批評のどちらも山ほど貰ったが、いわゆる王道には背を向け、自分の好きなこと、心魅かれることだけを脇見せずにしてきたと思う。反骨精神と権威や組織嫌いは、焼跡闇市時代に少年期を過ごしたせいかもしれない。園田高弘さんと中村紘子さんの丁度中間の世代である。これまでの人生はとても面白かった。大木正興さんの批評は私が貰った最高の批評であり、これからの人生もそのように音楽が出来たら幸せだと思っている。